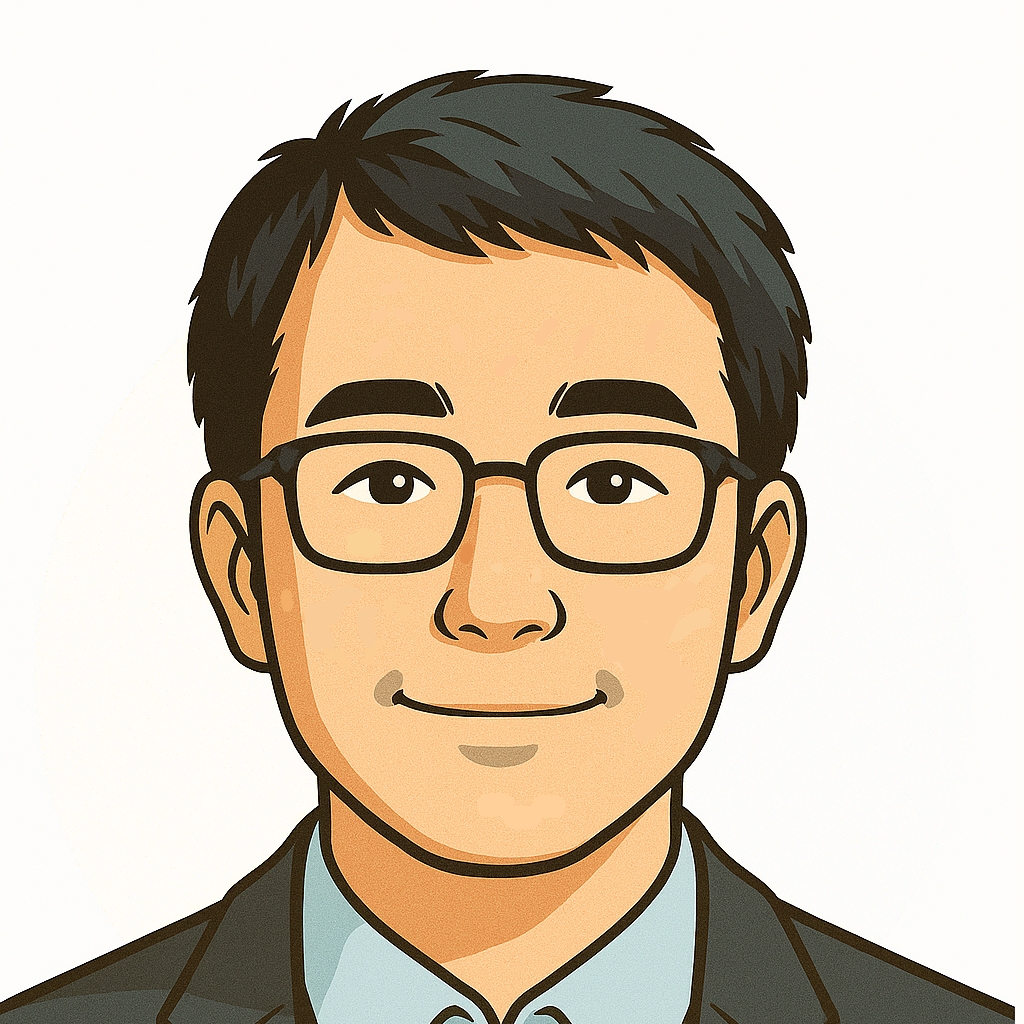【元管理者が解説】見守りカメラの危険性とは?安全に使うための3つの鉄則
「見守りカメラを付けたいけど、なんだか怖い…」「ハッキングやプライバシーの問題は大丈夫?」
離れて暮らすご家族や介護施設での安全確保に、見守りカメラは非常に便利なツールです。しかしその一方で、「監視されているようで嫌だ」「映像が流出したら…」といった危険性や不安を感じるのも当然のことです。
この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として見守りカメラの導入と運用に深く関わってきた私が、その「危険性」の正体と、それらを乗り越えて安全と安心を手に入れるための具体的な方法を徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、見守りカメラは「怖いもの」ではなく、正しく使えば「あなたと大切な人を守る、心強い味方」になることが分かります。
【結論】見守りカメラの危険性は2種類。そして、どちらも対策可能!

介護AI戦略室:イメージ
見守りカメラに潜む危険性は、大きく分けるとたった2種類です。そして、どちらも正しい知識と手順で対策することができます。
- 人間関係の危険性:プライバシー侵害、信頼関係の崩壊など、カメラの使い方や人の感情に起因するリスク。
- 技術的な危険性:ハッキング、サイバー攻撃による情報漏洩など、機器やネットワークに起因するリスク。
ここからは、これらの危険性を乗り越えるための「3つの鉄則」を具体的に見ていきましょう。
鉄則①【ルール作り】設置する前に「話し合って決める」ことで人間関係のリスクを防ぐ

介護AI戦略室:イメージ
技術的な対策の前に、最も重要なのがこの「ルール作り」です。カメラを設置する前に、関係者全員で以下の項目を話し合い、書面に残しておきましょう。これが、信頼関係を損なわないための最大の防御策となります。
- 目的の明確化:「なぜ設置するのか?」を具体的に決めます。(例:「夜間の転倒防止のため」「日中の安否確認のため」など)職員の監視など、目的外の利用は絶対に行わないことを共有します。
- 撮影範囲の限定:どこを撮影し、どこは撮影しないのかを決めます。(例:「リビング全体は映すが、トイレや脱衣所は絶対に映さない」)
- 閲覧権限者の指定:「誰が、いつ、どのような場合に映像を見ることができるのか」を限定します。(例:「緊急時のみ、長男と長女が確認する」)
- 録画データの管理:録画するのか、しないのか。録画する場合、保存期間と削除方法を決めます。(例:「録画は行わずリアルタイム視聴のみ」「録画は7日間で自動上書き削除」)
【元管理者の視点】
私が管理者だった施設でも、カメラ導入前には必ず利用者様・ご家族・職員を集めた説明会を開きました。「皆様の安全を守るためです」という目的を丁寧に伝え、同意書をいただく。このプロセスを経ることで、カメラは「監視の道具」ではなく「安心のパートナー」として受け入れられました。丁寧な対話が、テクノロジーへの信頼を生むのです。(参考:厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」)
鉄則②【機器選び】「安全なカメラ」を選んで技術的なリスクを減らす

介護AI戦略室:イメージ
全ての見守りカメラが同じ安全性を持っているわけではありません。ハッキングなどのリスクを減らすために、購入時には以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- 信頼できるメーカーか:国内メーカーや、世界的に実績のある大手メーカーの製品を選びましょう。安価すぎる無名ブランドの製品は、セキュリティが脆弱な場合があります。
- 通信の暗号化に対応しているか:「AES」「SSL/TLS」といった強力な暗号化技術に対応している製品を選びましょう。これにより、通信途中で映像を盗み見られるリスクが大幅に減少します。
- 国内にサーバーがあるか:クラウド録画を利用する場合、データが保存されるサーバーが日本国内にあるメーカーの方が、日本の法律に準拠した管理が期待でき、より安心です。
- ファームウェアの更新があるか:メーカーが継続的にセキュリティアップデートを提供しているかを確認します。アップデートが止まった製品は、新たな脅威に対応できず危険です。
パナソニックの「HDペットカメラ」やTP-Linkの「Tapoシリーズ」などは、これらのセキュリティ要件を公表しており、初心者でも比較的安心して選べる製品です。
鉄則③【設定・管理】「初期設定のまま」が一番危険!

介護AI戦略室:イメージ
安全なカメラを選んでも、設定が甘ければ意味がありません。ハッキングの多くは、利用者の簡単なミスが原因で起こります。
- パスワードを必ず変更する:購入時の初期パスワード(例: “admin”, “12345”)のまま使うのは、ドアに鍵をかけずに外出するのと同じです。大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた、推測されにくい独自のパスワードに必ず変更してください。
- Wi-Fiルーターのセキュリティを強化する:カメラだけでなく、その接続先であるWi-Fiルーターのパスワードも強固なものにし、ファームウェアを最新の状態に保ちましょう。
- ファームウェアを常に最新にする:メーカーから新しいファームウェア(カメラを動かすソフトウェア)の更新通知が来たら、必ずアップデートしてください。これにより、新たに見つかった脆弱性が修正されます。
これらの対策は、見守りカメラを安全に使うための最低限の義務です。(出典:NTTコミュニケーションズ「令和5年度 重要 IoT 機器のセキュリティ対策に係る調査の請負」)
【未来の安心】AIカメラは「プライバシーを守る」という選択肢

介護AI戦略室:イメージ
「それでも、常に見られている感じがするのは嫌だ…」という人間関係のリスクを、さらに一歩進んで解決するのがAI搭載の見守りカメラです。
従来のカメラは「映像をただ流す」だけでした。しかしAIカメラは、カメラが「見て、考えて、知らせる」ことができます。
- プライバシー保護機能:AIが人の顔やプライベートな空間を自動で認識し、モザイクをかけたり、映らないようにしたりできます。
- 異常検知・通知機能:AIが「転倒した」「ベッドから起き上がった」「普段と違う動きをしている」といった危険なイベントだけを検知し、その瞬間だけを通知。これにより、家族や職員は24時間映像を監視する必要がなくなり、プライバシーが守られます。
【これからの見守り】
AIの活用は、「見守りたい」という安心感と、「見られたくない」というプライバシーを両立させる画期的な解決策です。危険な瞬間だけを的確に知らせてくれるAIは、介護する側・される側双方の心理的負担を大きく軽減します。これは、テクノロジーが人の心に寄り添う、新しい介護の形です。
まとめ:正しい知識があれば、見守りカメラは最強の味方になる
この記事では、見守りカメラの危険性と、それを乗り越えて安全に活用するための3つの鉄則を解説しました。
-
- 危険性は「技術的な危険性」と「人間関係の危険性」の2種類に分けられる。
- 【鉄則①】設置前に「目的・範囲・権限」などのルールを全員で話し合い、人間関係のリスクを防ぐ。
–
【鉄則②】信頼できるメーカーの「安全なカメラ」を選び、技術的なリスクを減らす。
-
- –
【鉄則③】「初期設定のまま使わない」。強固なパスワード設定とアップデートを徹底する。
-
- –
AIカメラは、プライバシーを守りながら安全を確保する、新しい選択肢である。
見守りカメラは、使い方を間違えれば危険な存在になり得ます。しかし、今回ご紹介した鉄則を守れば、それはあなたとあなたの大切な人を、24時間365日静かに見守り続けてくれる、最も信頼できるパートナーとなるでしょう。